タイトルの通り、4条1項11号の商標審決に焦点をあてて、どのような結果がどれくらいの割合で含まれているかを数えてみました。
データベースで確認できた最新111件、期間にして2024年9月19日~12月5日に出された審決になります。(ぞろ目でキリがいいと思ったんですが、今思うと中途半端な調査ですね)
まず、総数111件は、全て拒絶査定不服審判の案件でした。無効審判が含まれていないのは、特許庁の審査がよく働いていて、審査段階で指摘されていない先行登録商標を探すのが難しかったからでしょうか。
このうち、原査定取消で登録になったものが、108件(約97.3%)、残念ながら請求不成立となったものが3件(2.7%)という内訳になっています。なんと、ほとんどの審判では、拒絶査定が覆っていたようです。拒絶査定となった全体件数が不明なので、やみくもに拒絶査定不服審判を請求するわけにはいきませんが、登録を希望する代理人としては、なかなか期待が持てる数字です。
登録になったものの詳しい内訳をみていきましょう。
まず、登録になったもののうち、指定商品役務の削除補正や、移転登録、取消審判で引例を消滅させるなどの手段で拒絶理由を克服したものは、36件(総数の32.4%、登録案件の33.3%)です。知財戦略・経営戦略でより狭い確実な権利をとりにいったり、交渉を駆使したり、審決の文章には表れてこないドラマがあったのでしょうね。
その他の72件(総数の64.8%、登録案件の66.7%)が、弁舌を尽くして審判官を納得させたものになります。ここはまさしく、弁理士の腕の見せ所かもしれません。
ここからさらに、登録となった判断の根拠で分けてみます。
すると、指定商品役務の非類似が根拠となって登録となった件が、5件(総数の4.5%、登録案件の4.6%)ありました。
これには、J-PlatPatで公表されている商品役務の類似群コードに捉われない斬新な発想が大事……ではなく!!審査基準に従い、1点1点確実に立証していくことが必要です。
①生産部門・②販売部門・③原材料及び品質・④用途・⑤需要者の範囲が一致するかどうか、⑥完成品と部品との関係にあるかどうか
①提供の手段,目的又は場所・②提供に関連する物品・③需要者の範囲が一致するかどうか、④業種・⑤当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか、⑥同一の事業者が提供する者であるかどうか
今回、指定商品役務の非類似を勝ち取った5件は、いずれもしっかりとした主張がなされていました。
そして残りが、商標の非類似が根拠となった件で、67件(総数の60.3%、登録案件の62.0%)ありました。
さらに分けると、結合商標か否かが争点となったものは、40件ありました。本願商標と先行登録商標とを比較する際に、はたして商標の要部を抽出して商標の類否を判断してもよいか、という点ですね。ちなみに、請求不成立となった3件のうち2件でも、結合商標か否かが争点となっていましたが、本願商標から要部を抽出して比較できると判断され、引例と類似すると判断されています。
残った27件が、結合商標であるか否か(商標の要部の抽出をするかどうか)に関係なく、引例との非類似が認められた件です。拒絶査定を出した審査官に真っ向反対の立場ですから、外観・称呼・観念を丁寧に比較して主張していく必要がありますね。
以上、たまには数字だけ追いかけてみるのもいいかと思って、あえて個別案件への言及は除かせていただきました。
[担当:岩田]
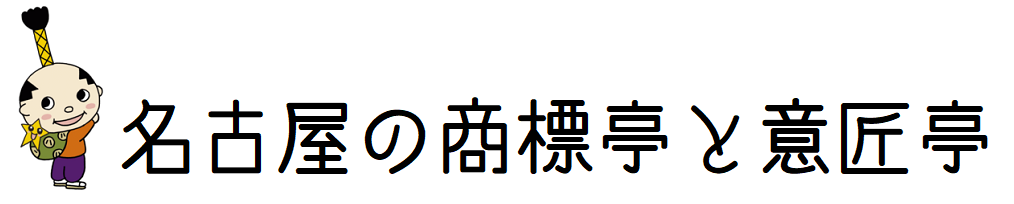
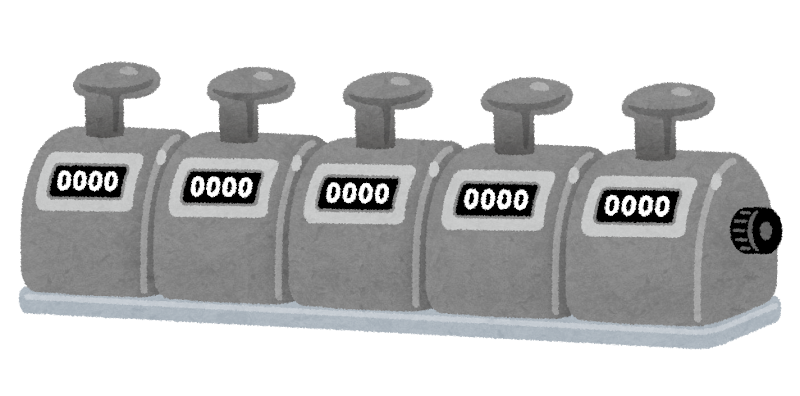



コメント