日本弁理士会関西会主催の令和6年度国際情報委員会 実務研究成果報告会を拝聴いたしました。
外国特許のテーマは、最近流行りのAI関連発明の国際調査比較でした。
近年どうにも減少気味な国内特許出願件数もなんのその、AI関連発明の出願件数は10年で約10倍程度に増加しているというから、第三次AIブームの波は大きいようです。
そして外国商標のテーマは、日本でも昨年2024年4月に導入された商標の同意書、コンセント制度でした。
復習のためにまとめておきます。
韓国でも2024年5月にコンセント制度が開始しており、こちらは日本と違って、共存同意書があれば先行商標との混同の有無にかかわらず、商標登録が認められます(さすがに商標、指定商品役務が同一の場合は除かれますが)。
ただし、対象となる商標登録(出願)を個別に指定した同意書が必要であり、「今後出願される商標の一切に対する同意」のような、包括的な同意書は認められません。
また、期限・地域制限・法律効果の一部排除などの条件付きの同意書も認められず、粛々と共存を合意する指定商品役務を記載します。
同意書の存在ひとつで先行登録の存在を理由に拒絶されない、この韓国のような制度を、完全型コンセント制度と呼びますが、採用している国は多くありません。
日本を含めた大部分の国は、先行登録商標の商標権者の同意がある場合であっても、出所の混同を生ずるおそれの有無について、審査官の審査が行われる留保型コンセント制度となっています。
今回の報告会に日本の内容は含まれていなかったので個人的な印象ではありますが、日本だとこの審査のハードルが高く、同意書があっても出所の混同が生じないとの立証が難しくなっているような雰囲気があります。消費者保護の意識が高いので、あまりコンセント制度に乗り気じゃないんでしょうね。
さて、台湾は、日本と韓国の間のような雰囲気で、留保型コンセント制度ではありますが、先行商標権者の同意があれば、それが明らかに不当でない場合、その同意書は認められます。
拒絶理由通知書に、「出願人が引用商標の所有者等に商標共存同意書に署名を求めることができる」というようなコメントが記載されていることがあり、これがあると通常、同意書の提出で拒絶理由を解消できるという制度設計のようです。
また、韓国とは違って包括的な同意書が認められており、商標の態様が記載されていれば、登録番号を記載する必要はないため、将来の同一類似商標の同一類似指定商品役務についても記載しておいたり、実際に後の出願で援用できたりします。
ただし台湾においても、同意書の条件や期限を記載することはできません。
これに対照的なのが米国の制度で、条件付きの同意書の価値を明確に重く見ています。
(1) 当事者が混同を回避する方法についての説明
(2) 商標が互いにどのように異なり、「商業的印象」が異なるかについての説明
(3) 各当事者の商品・役務が互いにどのように異なり、異なる取引チャネルを通じて販売され、価格帯が異なり、同じ消費者を対象としておらず、使用分野が制限されていることについての説明
(4) 実際に混同が発生した場合に当事者が講じる措置についての説明
(5) 商標がすでに長期間、混同なく平和的に共存していることについての説明
(6) 商標の使用の地理的制限
これらのような条件付き同意書のことを、米国商標審査便覧(TMEP)では、
“clothed” consent agreement(「着衣」の同意書)と呼んでおり、「着衣」の同意書が、混同の可能性が低いという結論に有利に働くことが明文化されています。
「着衣」の同意書に対して、需要者間の混同をどのように回避するかを説明していない同意書は、
“naked” consent agreement(「裸」の同意書)となり、提出しても効果を発揮しません。
同意書の認められるハードルが高い日本でも、米国にならって、出所の混同のおそれを否定するために、しっかりと服を着こんだ同意書を準備する必要がありそうですね。
[担当:岩田]
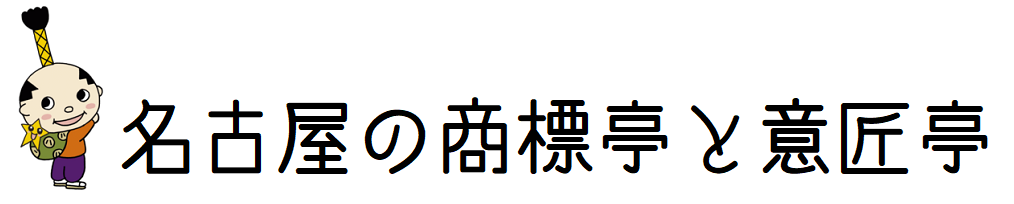




コメント