私、日本弁理士会東海会の委員会活動で、知財周辺法委員会という委員会に所属しております。
知財周辺法委員会では、通常弁理士が取り扱う4法(特許法、実用新案法、意匠法及び商標法)を除く知的財産関連法(著作権法、不正競争防止法、種苗法等)の、主に判例を年間を通じて研究しています。
その知財周辺法委員会の年度末の集大成、成果発表会が、昨日行われました。
1年の間に事例研究を行った不正競争防止法と著作権の判例の中から1件を選んで各委員が発表する発表会。持ち時間は一人20分ほど。
私にとっては、昨年に続いて2回目の発表になりますが、20分で説明し切るのは結構難しいんですよね…かといって、説明が足りなければ、受講者が理解できなくなる心配もありますし(ちなみに、私は著作権法の判例の発表でした)。
そこでギリギリのタイミングではありましたが、前日の日曜日に、ちょうど春休みで帰省していた息子に発表を聞いてもらい、発表の練習をしました。
1回目で分かりにくかったところなどを指摘してもらい、2回目も。。。
練習のかいあって、滑らかに説明できるようになり、本番は時間内におさまりました。息子くん、快く協力してくれてありがとう!
来年度も引き続き同じ委員会で活動しますが、弁理士会でも種苗法や地理的表示等のさらなる理解が要請されたり、著作権法でもAIが関わってききたりと、研究対象はどんどん多様化しつつあり、荷が重くなってくるので、ついていけるかどうか若干心配でもあります。
[担当:上田]
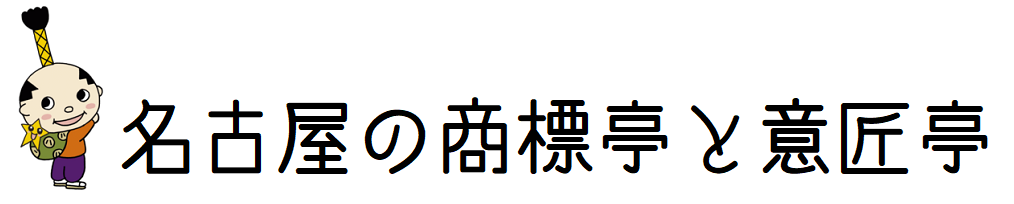


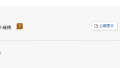
コメント