名古屋は桜の満開を迎えております。
寒暖差のはげしい近頃、服装を選ぶ助けにと天気予報をみるついでに、ついつい桜の開花情報も調べてしまいますから、この週末にでもお花見に出かけようと思います。
桜の季節を迎えると、食べたくなるのが団子と桜餅。
今日は、桜餅の話をしましょうか。
名古屋で見かける桜餅は、いわゆる関西風といわれるもので、道明寺粉を蒸して練ったつぶつぶの生地でまんじゅうのようにあんこを包み込んだ桜餅です。「道明寺風桜餅」などとも呼ばれることもあります。
これに対し、関東では、白玉粉と薄力粉でできた生地をクレープのように薄く焼いて、二つ折りの中にあんこを挟み込んだ桜餅があります。こちらのいわゆる関東風桜餅は、「長命寺風桜餅」などと呼ばれることもあります。
どちらも薄紅色の生地と、仕上げに桜の葉で包んでいるところは共通し、春の香りを食卓に運んでくれます。
由来としては、江戸時代に、東京の長命寺で桜の落ち葉掃除をしていた門番の方が思い付き、門前で売り始めた関東風の桜餅が起源といわれており、隅田川のほとりにある「長命寺桜もち」の店舗で伝統の味を食べることができます。
関西風の桜餅は、この関東風の桜餅を参考にしたものが起源といわれており、もち米を原料にした「道明寺粉」を使っていることから、道明寺と呼ばれているようです。
さて、商標審決を見ていますと、「長命寺桜もち」が拒絶査定を乗り越えて登録になっていました。
出願人は、先述の「長命寺桜もち」の11代目当主様で、指定商品は「さくら餅」。
審査では、桜餅を取り扱う業界において、「関東風の桜餅」程の意味合いで使用されている実情があるとして、商標法3条1項3号(及び4条1項16号)の拒絶査定を受けていました。
審判の判断は、以下の通り。
そして、請求人の主張及び提出された証拠(甲第1号証ないし甲第139号証)によれば、請求人及びその親族は、1717年(亨保2年)に「さくら餅」を考案し、墨田区向島の「長命寺」の門前で売り始めて以来、本願商標やこれに類似する商標(登録第917772号商標)を、自身の業務に係る商品「さくら餅」について長年使用しており、当該商品について、請求人等による広告宣伝活動が行われたほか、書籍や雑誌、テレビ番組などにおいてしばしば紹介された事実も認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品に係る取引者、需要者において、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、一定程度知られているものといえる。
また、当審において職権をもって調査するも、請求人及びその親族が「さくら餅」を考案したことから、「関東風の桜餅」として「長命寺桜もち」と表現されている例が一部あるとしても、この表現とする明確な理由は発見できず、また、本願の指定商品を取り扱う分野において、原審説示のごとく「長命寺桜もち」の文字や「長命寺」の文字が、「関東風の桜餅」を指称するものとして、取引者、需要者に広く理解、認識されているといえるほどに、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、特定の意味を有しない造語として認識されるといえるものであって、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
出願人の商品の知名度をある程度認めながらも、3条2項ではなく、そもそも「関東風の桜餅」を指称するものとして「長命寺」が使用されていないという判断はいささか驚きです。
とは言え、せっかく登録を勝ち取ったのですから、関東風桜餅の代名詞ではあっても普通名詞とはなってしまわないように、しっかりと守っていっていただきたいですね。
ちなみに、「道明寺桜餅」は登録されていないようですが、こちらは原材料の略称でもあるので、長命寺よりも3条の拒絶が来る確率が高そうです。
[担当:岩田]
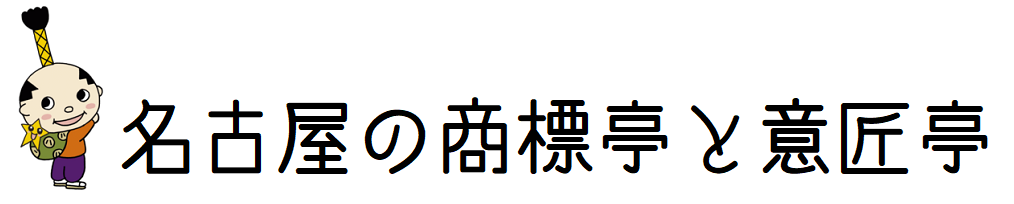


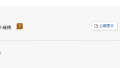

コメント