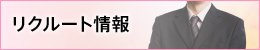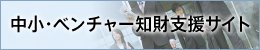商標
- ホーム
- 商標
トピックス
-
ご相談はオンラインでも可能です!
- 2020.06.08
-
知財カスタイマイズセミナー
- 2013.12.16
-
令和6年外国出願補助金
- 2024.05.13
-
2023年法改正のまとめ②
- 2024.04.12
-
2023年法改正のまとめ①
- 2023.12.08
-
【著作】並行輸入と商標権侵害 -「輸入品の真正性の要件」及び「品質管理性の要件」-
- 2022.10.28
-
【著作】[新版]商標法コンメンタール
- 2022.03.04
-
【著作】川上側企業から川下側企業への商標ライセンス契約
- 2022.01.14
-
中部経済新聞掲載記事「商標登録はゴールではない~登録後の保守運用が大切です~」
- 2021.07.14
新着情報
-
【カナダ商標】登録官主導の不使用商標取消のパイロットプログラムがスタート
- 2025.07.04
-
【中国商標】不使用取消審判請求時の提出書類要件が厳格化される
- 2025.06.13
-
【米国商標】登録商標の監査を強化
- 2024.12.04
-
【ブラジル商標】ブラジル、広告的要素を含む商標出願の受付開始
- 2024.11.12
-
【米国商標】 2024年第3四半期のファーストアクション期間
- 2024.10.09
-
【インド商標】契約職員によりなされた商標に関する決定が再検証される?
- 2024.08.28
-
【台湾商標】加速審査制度(早期審査制度)が導入されました
- 2024.07.23
-
令和6年外国出願補助金
- 2024.05.13
-
2023年法改正のまとめ②
- 2024.04.12
-
AIGI MAGAZINE 12月号
- 2023.12.20
あいぎ特許事務所は若い事務所ですが、多くのお客様にリピーターになっていただいたことで着実に成長してまいりました。これは、お客様とのコミュニケーションを大切にし、誠実さをもって業務に当たってきたからだと自負しております。
加えて、あいぎ特許事務所の規模が適切であるからこそ、下記のユニークな特徴を併せ持つことができ、これが成長の一助を担っていると感じております。
意匠商標部門の強み
1.商標に関する専門性
(1) オモテからは見えないご提案
ブランド保護のため・使い易くて強い商標権を得るためには、商標出願書類や商標公報を見ただけではわからない様々な工夫や考慮が必要です。一つの商標を決定するにも、業種特有の事情、社名・ハウスマーク/ファミリーネーム/ペットネームの別、BtoB/BtoCの別、使用形態等、考慮項目が多岐に亘り、多観点から検討する必要があります。
あいぎ特許事務所では、商標出願をご依頼いただいた際には、必ずカウンセリングを行い、商標登録でなにを達成したいのかの本質を把握するため、前記の考慮項目を伺って検討させていただきます。また、ケースによっては、より良い商標登録・商標権の取得ができるよう改良等のご提案をさせていただきます。
(2) 商標に関する独自データの活用
商標に関し、専門性の高いアドバイスをご提案するためには、今まで蓄積してきたノウハウを、判例・審決の動向やお客様の業界の動向に合わせて柔軟に活用することが求められます。この点、あいぎ特許事務所では、各メンバーが得たノウハウを集積し、メンバー間で共有し合う体制を整えております。また、商標の最新動向に関する情報や判例・審決をup-to-dateに収集し分析を行っております。
これらの活動を土台とした独自データを活用することで、お客様の業種、販売形態、事業展開の態様等を考慮しながら、実情に即した合理的な提言を行い、かつ、効率的・効果的な戦略を立てることができます。
2.知的財産権に対する総合的支援
(1) 知的財産権に係るワンストップサービス
あいぎ特許事務所では、出願業務だけでなく、お客様の戦略に対応して「調査」、「診断」、「鑑定」、「相談」、「セカンドオピニオン」、「顧問契約」を含む総合的なサービスを提供しております。また、弁護士との提携により、紛争処理にも対応可能です。
(2) 特許部門との連携
一つの製品を、デザイン面・ブランド面・技術面等のどの観点で保護すると最も効率的・効果的であるかの選択には、知的財産に関する個々の法律に関する深い知識だけでなく、知的財産権法全般に亘る広い視野を持つことが求められます。このため、あいぎ特許事務所では、意匠商標部門と特許部門との連携が不可欠であると考え、頻繁に情報交換しながら相互に協力・支援し合う体制を整えています。